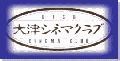 |HOME|
|HOME||
Mr.TanakaGoes to the Movies |
大津シネマクラブ 田中 健
| バック・トゥ・ザ・フィルム⑤ 『真夏の興行を見る』↓ |
|
ここ最近、下賀茂神社の古本祭りに出かけるのが真夏の行となった。これはもう暑いというほかなく、境内にずらりと並んだ古本店のテントを一軒ずつ覗いていくことの何と体力のいることか。 今年はそこで吉村公三郎の自伝「キネマの時代」を買った。湖国を代表する巨匠監督として日本映画史に一時代を画した人だが、ぼくは30年近く昔に滋賀県の第三セクターの機関誌を編集していた折り、無謀にもこの巨匠に電話をかけ、随筆を書いてもらったことがある。 ブライアン・シンガーの「スーパーマン リターンズ」も概ね評判がいい。たしかに、この映画の成功はヒーロー役者がクリストファー・リーヴ以上に決まっているからだろう。 |
| バック・トゥ・ザ・フィルム④ 『プロデューサーズ』↓ |
|
ずっと気になっていたことが氷解した。というのも、当クラブ4-5月劇場鑑賞作品「プロデューサーズ」の内外の評価が割れていて、それがひっかかっていた。海外の評価は概ね不評で、星にすると1つから2つの評価である。ところが、わが国の評判は上々で、しかも玄人筋もほめている。 一方、今回のリメイクをクソミソの海外でも、オリジナルのメル・ブルックス版は4つ星評価ということになっている。こうなると原作のメル・ブルックス版をどうしても見たいという気持ちになる。近くのレンタル店を探したが見つからなかった。あきらめていたところ、みなみ会館でやるというので急いでかけつけた。 一般論として、オリジナルをリメイクが超えることは至難のワザである。なぜならば、芸術でも芸能でも、その存在価値はほとんどオリジナル性にあるのだから、そもそもリメイクあるいは模倣作を作ろうという時点で評価されることを半ば投げているのである。 メル・ブルックス版は恐らく向こうの人が見たら滅茶苦茶面白いのだろうが、トーキー後の喜劇の宿命として異国語の国では本来の面白さが伝わりにくい。だから、4つ星という評価は日本人にはぴんと来ない。しかし、少なくとも、新作よりは面白かった。その第一は既に指摘したように、そのオリジナリティにあるが、加えて、これは紛れもなく映画として書かれ撮られたからにほかならない。 しかし、ずばりいうと、一番の面白さの違いはキャストである。いかさま興行をしかけるプロデューサー役のゼロ・モステルは斯界の大御所であり、うまいというほかない。主役は当然かれであり、脇役の会計士を演じるのがコメディアンのジーン・ワイルダー。この人はダニー・ケイ型のコメディアンで神経質な動きをする。 とりわけ笑ったのはゲイの演出家の登場で、その秘書がギリシャ人風の風貌なのがケッサク。あのメイクアップは「甘い生活」のパロディかと一瞬思った。ああいうメイクの男が確か出てきた気がする。これなども新作は旧作をなぞっただけで、毒気もない。 |
| バック・トゥ・ザ・フィルム③ 『オスカー・ゴーズ・トゥ・・・』↓ |
|
前回推奨した芝山幹郎の「映画一日一本」(朝日文庫)を同じく前回愛読していると書いた中日新聞、小林信彦のコラムが先頃取り上げているのを読んで思わずニンマリしてしまった。 ところで、アカデミー賞の方だが、最有力と目された「ブロークバック・マウンテン」が監督賞こそ獲得したが、大方の予想を裏切ってダークホースと目された「クラッシュ」に作品賞を持って行かれた。 作品賞を得た「クラッシュ」は、なるほどよくできた作品だと思う。かけがえのない商店を何者かによって破壊されるペルシャ人の商人が登場するが、かれいわく「アラブとペルシャの区別などつかない」のである。 主演女優賞を取った「ウォーク・ザ・ライン/君につづく道」もなかなか楽しい作品だった。ホアキン・フェニックスがジョニー・キャッシュを演じる伝記映画だが、音楽場面のノリがいい。
アカデミー賞でときどきよくわからないのは主演と助演の線引きである。「シリアナ」のジョージ・クルーニーはタイトルでは立派に第一位の主演級だ。しかし、ご存じのようにクルーニーは助演男優賞にノミネートされ、最優秀賞に輝いた。 |
| バック・トゥ・ザ・フィルム② 「ベスト10の季節」↓ |
ぼくが最近愛読している新聞の連載コラムは職場でとっている中日新聞の小林信彦のテレビや映画を話題とした時評的なエッセイと、日経新聞の土曜版別刷プラスワンに連載中の芝山幹郎のコラムである。 その芝山のコラムが本になった。朝日新聞社から出ている朝日文庫「映画一日一本」がそれだ。かねてから、このコラムの鋭い筆致には敬意を払って読んでいたのだが、おそらく残念ながらいまどきの映画評論家ごときには真似のできない鮮やかな分析に、ただただ脱帽しないわけにはいかないのである。 本職が翻訳家で映画評論にも手を染めている人にはほかに井上一馬や青山南がいる。しかし、はっきり申し上げてこのふたりは素人以外の何ものでもない。それは、ふたりの書いたものを読めば一目瞭然であり、井上の大仰な著作「アメリカ映画史の教科書」などは、ほとんど受け売りではないか。 ところが、である。芝山さん(敬意を表して)の書くものは専業の映画評論家ですら地にひれ伏すくらいの新しい発見に満ちた批評であり、映画とはこう見るのだ、と教えられることも多く、とくに視覚的なテクニックに言及する姿勢がみごとである。ぼくはこれを読むごとに自信をなくし、なんとうまいんだろうと、ため息ばかりつく。 ため息が出るのはぼくばかりではないらしい。このほど届いたキネマ旬報最新号でも新刊案内「本の映画館」に「強靱な個と映画史を編んだ魅惑の映画地図」と題して本書が取り上げられている。副題の「DVDで楽しむ見逃し映画365」とあるように、格好のビデオ・DVD案内書となっているので、ぜひ一読をお奨めしたい。 そのキネマ旬報ベスト10が発表された。海外では何といってもアカデミー賞の行方が気になる季節ではあるが、年末年始にかけて国内で一番気になるのがこのベスト10。間違っても日本アカデミー賞の行方など気にならない。日本アカデミー賞より毎日映画コンクールの方がよほど権威があるから、誰も気にしないのである。 残念ながら毎日映画コンクールは新聞社の名前が冠してあるからほかの新聞が取り上げないだけである。そんなことはどうでもよろしい。世界最古のベスト10として知られる旬報のトップ10は既に新聞発表されたとおりであるが、邦画1位「パッチギ!」、2位「三丁目の夕日」、3位「いつか読書する日」、4位「メゾン・ド・ヒミコ」、5位「運命じゃない人」と続き、外国映画は1位「ミリオンダラー・ベイビー」、2位「エレニの旅」、3位「亀も空を飛ぶ」、4位「ある子供」、5位「海を飛ぶ夢」である。 邦画では「男たちの大和」が、洋画では「スター・ウォーズ」と「キング・コング」が10内に入選しているのがご愛敬だが、それにしてもいつにない渋いベスト10だと思った。 こう見るとたしかに邦画の健闘が目立つ。1位から5位までの上位作品のうちで、ぼくはたいてい見ていないことが多いのだけれど、去年は4本まで見ている。反対に外国映画の方は5作品のうち2本しか見ていない。たしかに、巷間いわれたようにアメリカ映画の影が薄くなって、邦画が元気だった。5位の「運命じゃない人」を見ていないので4位までに限っていえば、どれがトップに来てもいいくらいの出来だったと思う。 個人的には「いつか読書する日」の完成度に感服した。田中裕子の主演女優賞にも異存がない。ぼくはむかし小学校のころ、脱脂粉乳というとんでもない代物を6年間飲まされて、今では牛乳を見るだけで吐き気がするほど大嫌いになってしまったが、そのぼくが見ても感心したのだから尋常ではない。 「パッチギ!」もやたら面白かった。爆発するようなエネルギーを感じた。一方、同じ被差別を扱った「メゾン・ド・ヒミコ」はむしろ沸々と内にたぎるような内攻的なエネルギーを感じさせた。特筆すべきは後半のダンス・シーンで、あのノリはいったい何なのだろう。すっかり降参して思わず引き込まれてしまった。主演のオダギリジョーもずいぶん成長した 外国映画の1位と2位は順当であった。これも入れ替わったってさほど不思議ではない。想像するに3位以下の作品はそれほど目立つものが無かったということなのではないだろうか。 ところで、「キング・コング」についてであるが、冒頭の小林信彦のコラムで「よく出来ているが長すぎる」と苦言を呈していた。しかし、ぼくは思ったほど長くは感じなかった。すっかり手中にはまって楽しんでいたのである。むしろ長いと感じたのは「男たちの大和」である |
| バック・トゥ・ザ・フィルム① 「戦後十年を経た懐かしい日本があった・・・」↓ |
| 昭和三十年代の懐かしい日本がそこにあった。「ALWAYS三丁目の夕日」のなかである。いまの日本を牽引するといわれる団塊の世代が少年時代を過ごした懐かしい日本だ。 ぼくは団塊の世代から数年あとに生まれたので、この時代の記憶はかすかに残る程度だが、それでも時代の空気はわかる。幼稚園にもまだ行かぬ年頃だと思うが、やはり近所の電器店に「月光仮面」を見に行ったりした。駄菓子屋に日光写真やメンコを買いに行った記憶がある。 東京タワーが建設中で、就職列車が走っていたころの東京・・・というより上野駅を起点に物語は始まる。 戦争から帰って腕一本で起こした自動車修理工場のおやじ(堤真一)が青森から集団就職でやってきた少女(堀北真希)を三輪自動車に乗って迎えに行くと、少女は何しろ有限会社の自動車会社に就職するとあって、どんな大きな会社だろうと胸ふくらませて待っている。ところが、つれて行かれたのは小さな町工場。人のいいおかみさん(薬師丸ひろ子)と腕白坊主が待っていた。 その向かいで駄菓子屋を片手間にやっている独身男(吉岡秀隆)は東大を出て文学を志し、日夜創作に取り組むが、一度として作品が入選したためしがない。志に反して少年雑誌に他愛ない冒険小説を書いては糊口をしのいでいるらしい。 かれがこのところ気に入っている飲み屋の女(小雪)に、知り合いの子どもだが身寄りがないので預かってくれと、小学生の男の子をまんまと押しつけられる。酔った勢いだとはいえ、引き受けてしまったものはどうしようもない。かくして、他人の子どもと暮らすはめになった三文文士と向かいの自動車修理工場の一家の日常がコミカルに描かれるのである。 おとなも子どももまだ純粋で、少なくとも庶民というものに邪心がなかった時代。もうそういう時代でしか、松竹新喜劇的な人情喜劇は通用しないのかもしれない。その懐かしい泣き笑いが、ここにはある。 大きな見せ場が三つあって、ひとつは自動車修理工場の夫婦が少女にクリスマス・プレゼントとして大晦日、青森行きの列車の切符を贈る場面。夫婦は、女の子が就職以来、お盆の藪入りもせず、ひたすら働いてきたことへの感謝の気持ちを表したつもりだが、どうも様子がおかしい。大晦日になっても一向に出発する気配がない。挙げ句に帰らないと言い出す。よく聞けば、自分は口減らしのために就職した、家に手紙を出しても返事も来ない、おそらく帰っても歓迎されない、捨てられたのだ、と少女はいう。 おかみさんが少女に手紙の束を見せる。少女の母親が夫婦にあてた手紙である。毎月、娘の安否を気づかう手紙が来るという。しかし、娘に里心がついちゃいけないから決していわないでくれ、と。さあ、早く支度してお母さんのところへ帰ってあげなさい、というおかみさんの言葉に少女は故郷へ急ぐのである。 ひとつは、駄菓子屋の男の子の母親がどこそこにいるという情報を聞きつけて、同級生の工場の倅がついてってやるから会いに行こうと促すシークェンス。結局、目的地まで行くが会えない。家に帰る電車賃もない。家では双方の家族が誘拐か、事故かと大騒ぎである。やがて、帰ってきた二人を見て雷おやじの町工場の父親が倅を殴ろうとした瞬間、さきにバシッという音がして、三文文士が居候の男の子を殴った。どんなに心配したかと、三文文士は子どもを叱るのである。 クライマックスは子どもの父親と称する会社の社長が現れ、運転手付きの黒塗りの高級車で男の子を迎えに来る。しかし、男の子は三文文士と別れたくなくて途中で降車して戻ってくる。三文文士も男の子がいなくなった空虚さでいたたまれなくなり後を追う。この二人が再び街中で会ってひしと抱き合う場面は、さながらチャップリンの「キッド」である。 気がつけば、あちらこちらですすり泣きが聞こえ、ぼくも何度か涙を拭った。隣に座っていた若い男の子まで泣いていた。人情喜劇でここまで泣かされるのは久しぶりである。 ぼくは原作の漫画をよく知らないが、戦前の小津安二郎の小市民喜劇やフランク・キャプラの人情喜劇に見る、人間への信頼に根ざしたほのぼのとした笑いと感動が立ちのぼる。 脇を固めるひとびともみんないい味を出している。三浦友和が空襲で妻子を亡くした町医者を淡々と演じ、あたらしもの好きの煙草屋の老婆に扮するもたいまさこがおかしい。母に会いに来た男の子を追い返す饅頭屋の主人を憎たらしく演じた石丸謙二郎、その男の子を迎えに来る成り上がりの社長を嫌みたっぷりに演じた小日向文世がともにうまい。 。 |
|
№164 「スイミング・プール」の普遍性↓ |
|
フランソワ・オゾンは近ごろ目が離せない作家のひとりであるが、「スイミング・プール」は「8人の女」の遊び心に「まぼろし」の作品的な完成度を加味した佳作といえる。 シャーロット・ランプリングが演ずるサラ・モートンという英国ミステリの女王は、ミステリ通ならすぐわかるように、戦前戦後を通じて英国探偵小説界で優勢を誇る女流作家たちを象徴している。 一般にはクリスティしか知られていないから、クリスティがモデルなどと思ったら大きな間違いで、クリスティの時代ですらドロシー・セイヤーズやマージェリー・アリンガム、クリスチナ・ブランドといった女流の大家が君臨したし、現代ではP・D・ジェイムズを筆頭にルース・レンデル、サラ・ウォーターズなど枚挙にいとまがない。まず、そこでにんまりさせられる。 余談だが、アメリカにはパトリシア・ハイスミス女史がいて、そのニューロティックな作風が本国では疎まれ不遇だった。当時、かの女の代表作を映画化したのはヒッチコックとルネ・クレマンであったが、いずれにも通底する倒錯性は巧みな演出で隠蔽された。 交換殺人による女房殺しというテーマのヒッチ作品について、その点が指摘されたのは近年のことであるが、クレマンの貧しい青年によるブルジョア青年殺しに倒錯性を発見したのはほかならぬ淀川長治であり、その感性は凄いといわざるを得ない。 アンソニー・ミンゲラのリメークを見れば淀川さんの勘の鋭さがわかる。もっとも、ミンゲラはハイスミスの原作を忠実に映画化したに過ぎないのだが。 なぜこんなことをいいだしたかというと、オゾンのテーマの普遍性がハイスミス女史のそれと共通するからである。さらにいえば我れらが木下恵介に共通するところがオゾンにはある。同じ倒錯性を性向としてもつ作家デレック・ジャーマンにない部分である。 オゾンの初期の作品はジャーマン同様、自己の性向に忠実なテーマ追求が目立ったが、「8人の女」から作風が普遍性を持った。木下恵介は時代的な制約からそうならざるを得ないところがあったかもしれないが、しかし、それだけではないと思う。 ふたりに共通するのは女性を描かせては右に出る者がいないという巧さではないか。つまり、キネマ旬報に誰かが書いていたように、女性の感性がわかるということだろう。もっといえば、「わかる」とはどういうことか。 それは、女性の感性を持っているからにほかならない。ヒッチコック作品ではいつも男優より女優が輝いて見える。ヒッチが倒錯性を帯びた作家だという指摘は既にあるが、こういう観点からも同じ傾向を見いださないわけにはいかない。 女性が描けないといわれた黒澤明(フォードがそうであったように黒澤は男の中の男だった)や、女性を描く気がなかったジャーマンとの違いがそこにある。サッフォーの末裔であるハイスミス女史は自己の倒錯性を発現する方法として男性を主人公に据えて知らばっくれた。このことが、かの女の作品に普遍性をもたらしたのは皮肉である。 「スイミング・プール」には賛否両論あるだろう。「アイデンティティ」がそうであったように、その手はずるいよ、という声が聞こえてくる。たしかにずるい。幾重ものルールに縛られたミステリとして見ればルール違反だという抗議もうなずける。 だが、はたしてこの作品を単なるミステリ映画の範疇に押し込めておいていいものか。むしろ、きわめて普遍性の高いテーマをもつ作品だといえないか。江戸川乱歩の名作として知られる「押し絵と旅する男」というきわめてシュールな短編がある。 三島由紀夫が何かで指摘したように、頭脳明晰な作家には優れた長編が書けない(当然、自己弁護にほかならぬが)というジンクスどおり、乱歩は本質的に短編作家であり、ときどき短編の中にミステリの範疇を超えた秀作を生んだ。オゾンの新作を見て「押し絵と旅する男」の白昼夢を思わず想起しないわけにはいかなかった。 ***** |
|
№163 探していた本のことなど↓ |
| ぼくは視覚的人間であると同時に活字人間であるのだが、前にも少し触れたとおり、インターネットというやつのおかげで、探し求めていた書籍が容易に手に入るようになったのはありがたい。
最近、突然魯迅に目覚め、無性に岩波書店版「魯迅選集」を読みたくなった。ネットの古書店で検索すると、全国の古書店の中で「魯迅選集」を扱っているところがたちどころにあらわれ、どこが一番安いかもわかる仕掛けだ。こうして入手した「魯迅選集」をいま舐めるように読んでいる。 しかし、どうしても見つからない本があって、たとえば「現代日本映画論大系」のうち第3巻と第6巻が欠落していたのだが、昨年のいつだったか、偶然通りかかった京都文化博物館内の古書市で第3巻を見かけ、格安で手に入れた。また、日本シナリオ大系」のうち第1巻だけが長らく欠けていたのだが、これは5月の連休に催される京都市勧業館での古書市で見つけ、すぐに購入した。 あと、ぼくが探し求めている書籍というと、佐藤忠男「木下恵介の映画」、中井英夫「月蝕領映画館」ぐらいとなった。 佐藤の該当作はたまにネットの古書店で見かけたが、うっかりしているうちに売り切れた。中井の方は目下、東京創元社が数年がかりで文庫版全集を刊行中だ。最近は1年に1巻しか出ていないようだ。それでもほぼ全巻に近いところまでこぎ着けた様子。「月蝕領映画館」(最終巻か)は今年か来年には刊行される見込である。 中井といえば戦後ミステリの金字塔と称される巨編「虚無への供物」が長らく絶版になっていたのをこの全集が取り上げ、最近では講談社文庫が復刊した。ぼくは30年以上前に講談社文庫で一読し、ミステリとしてよりも、その独特の雰囲気にすっかり魅せられてしまった。 三島由紀夫のよき理解者であり、わが郷土の生んだ巨星塚本邦雄や寺山修司、春日井建といった天才肌の前衛歌人を発掘した短歌界の名伯楽、中井英夫の功績は計り知れないものがある。中井の本領は幻想小説であるが、大衆を横目で軽蔑しながら孤高の領域に独自の文学を築いた。 「黒衣の短歌史」はぼくの愛読書のひとつである。早熟の文学少年だった中井と三島は根底でつながっており、「月蝕領映画館」には優れたヴィスコンティ論があったはずだ。作品は「地獄に堕ちた勇者ども」だったような気がする(あるいは「ベニスに死す」か)。 それから、思い出したが、竹中労「日本映画縦断」(全3巻)も気がついたときには絶版となっていた。嵐寛の聞き書き「鞍馬天狗のおじさんは」は筑摩文庫版で持っており、その後も逐次竹中労の著作が同文庫から刊行されているが、この本も文庫化されないものか。 竹中が週刊誌のルポライターをやっていたころ、祇園を取材する仕事が入って、会社(出版社)に吉井勇全集の購入費用を取材費として請求したという話を聞き、たまげたことがある。つまり、吉井勇全集を読まないと祇園は書けないというプロ根性である。 この人のような歯切れのいい、自由闊達な文章が書けたら、と思ったことがある。 ぼくは特段文学少年であった時代などないのだが、それでも文章の巧拙くらいはわかるようになって、いくら崇高なことが書いてあっても下手な文章というのは勘弁してほしいと思う。 いくらモデルが美人でも画家が下手では話にならないのと同じである。あるいは優れたテーマ、筋書きだけで映画の優劣が決せられないのと同じだ。 名文家にも二種類あって、技巧派と自然派に分けられる。この自然派というやつがなかなか到達できない領域であって、名文を書こうと思うとどうしても技巧に走ってしまう。志賀直哉やその志賀を「万年作文作家」と侮蔑した稲垣足穂は自然派名文家の代表選手ではないか。映画の文体もまた、同じことがいえ、さしずめ自然派の名文家は小津さん、といっておこうか。 ***** |
|
|